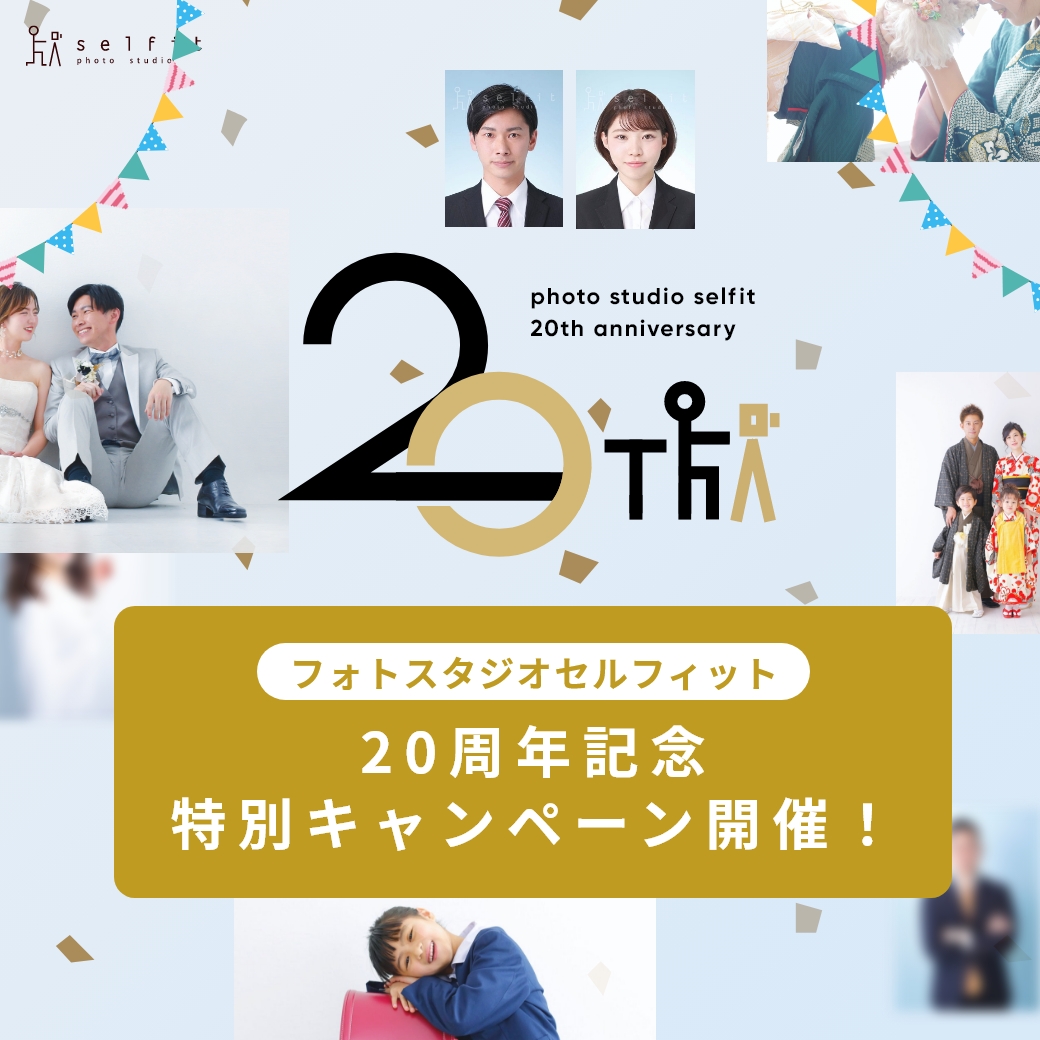「仕事が”楽しい”と感じたことは一度もなかった」Luup創業者が明かす“ハードモード”をあえて選ぶワケ
電動キックボードや電動アシスト自転車といったマイクロモビリティのシェアリングサービスを展開する株式会社Luup。
代表取締役CEOの岡井大輝さんは、学生時代のサークルで出会った仲間と会社を創業し、これまで起業家の道を歩んできた。だが、いざ事業を始めると、想像もしなかった数多くの困難が待ち受けていた——。
「これまで仕事が“楽しい”と感じたことはなかった」
そう話す背景には、どんな苦労があったのか。なぜ、ハードモードの人生を選んだのか。今回はLuup創業者のライフストーリーに迫っていく。
サークルでの出会いが起業のきっかけに

── まずは岡井さんの学生時代について教えてください。
学生時代は学業の研究とサークル活動の両方に打ち込んでいました。現在のLuupでCOOを務める牧田涼太郎やCTOの岡田直道をはじめとする共同創業者たちは、皆サークルで出会ったんです。
いわゆる「起業サークル」のような集まりではなかったので、純粋な友人関係から、互いに優秀だと思っていた仲間と「将来的に起業しよう」と話していて、一旦社会に出た後に合流して創業したのが今のLuupになります。
卒業直後に起業しようと考えたこともありましたが、その頃の学生起業では数千万円規模しか資金が集められず、50年後、100年後の日本社会に本当に必要とされる医療や介護、交通などの領域には挑めない状況でした。
また、こうした大きな課題に挑むには、まずは社会に出て経験を積んだ後に再び合流して事業を立ち上げる方が現実的だと考え、一旦はそれぞれ就職の道を選んだのです。

── 新卒では戦略系コンサルティングファームへ就職されましたが、そこで得たものは何かありましたか?
戦略コンサルの会社では、「仕事を進める上での基礎的な考え方」を学びました。メモの取り方や人との約束の仕方ひとつをとっても、本当に奥深いというか。例えば会議のメモを取るだけで、その人がどれだけ優れたビジネスパーソンかがわかってしまうんですよ。
当時お世話になっていた先輩は、次の会議、場合によってはその次の会議までの結論を予測してメモを書いていたのがとても印象に残っていますね。
単にAIで議事録を取って要約するというレベルではなく、自分の手で誰が何に気をつけるべきか、誰がいつまでに何を達成すべきかといった本質的なポイントを整理しているのを見ると、まさにコミュニケーションの真髄を学ぶ経験だったなと思います。
年上の大先輩から学び、2年間その下で働けた経験は、社会人としての土台とコミュニケーションの重要性を学ぶ貴重な時間でした。
Luup創業から今まで、仕事が“楽しい”と感じた瞬間はない?
── 2018年7月のLuup創業から7年が経ちましたが、これまでの道のりを振り返って率直にどう感じていますか?
創業当初、渋谷のワンルームにオフィスがあった頃は、今よりもずっと未熟で現実がまったく見えていませんでした。当時はここまでの道のりがものすごく大変だとは想像もしていなかったですね。本当に毎月のように厳しいご意見やフィードバックをいただくなかで、5個10個と改善を重ねてもそれ以上の課題が次々と出てくる。まさにそんな日々の連続で、正直なところ楽なことなんて一つもなかったんですが、それでも「やりがいはあった」と言えます。
正直に言って、楽しいと思って夜に寝たことが1日もないですね(笑)。いわゆる快楽的な“楽しさ”を求めているわけではなく、将来おじいちゃんになって振り返ったときに、「あの時の5年、10年は本当に意味のある時間だった」と胸を張って言える。これが、自分にとっての幸せなんだと思います。
なので、不思議な感覚なんですが、「今、仕事が楽しい」と感じた瞬間はこの7年間で一度もない一方で、「これまでを振り返って楽しかったですか?」と聞かれると「楽しかった」と答えると思います。
日々生活していくなかで、自分たちのサービスを街中で見かけると「嬉しいな」と思うことはあっても、それ以上に「次にやらなければならない課題」が常に目の前に現れるため、“ハードモードのゲーム”をやっているような感覚なんですよ。
「仕事は人生そのもの」。ハードモードの人生を歩む原動力
── ハードモードのゲームに取り組む原動力はどこにあると思いますか?
自分がどう生きたいかを考えた結果、「仕事とは人生そのもの」という風に捉えています。個人的に、仕事とプライベートの間に明確な境界をあまり設けていなくて、むしろプライベートの時間以上に有意義だと思える時間を、仕事の中で過ごしたいんですね。
だからこそ、会社としても「今の日本や人類にとって意義のあることをしたい」と思っていますし、社員にも「人生の一部を会社の挑戦に貸してください」と伝えています。僕たちは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションのもと、最初は電動アシスト自転車からサービスをスタートし、次に電動キックボードを導入しました。
コンビニとの提携が実現したときには、週末になるとスーツ姿の方から若い人まで、多くの方がLUUPを利用してくれるようになりました。街中でその光景を見かけると本当に嬉しい気持ちになる反面、「安全に乗れているだろうか」「ルールを守ってくれているだろうか」といった不安も同時に感じます。
それでも、この仕事を通じて人々の暮らしが少しでも便利に、豊かになっていると実感できるのが、自分にとって最大のやりがいになっています。
「技術への投資」と「現場の誠実な運営」が不可欠
── 事業で今、注力していることを教えてください。
安全対策については、街の方々やSNSで寄せられる声を聞くうちに、まだまだ足りていないことを痛感しています。そのため、今後も引き続き力を入れていく必要があると考えています。
現在、安全対策の基本方針として3つの柱を掲げていて、まず1つ目は「交通ルールをきちんと知ってもらうこと」です。電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は2023年の法改正で新たに定義された車両区分なので、まずは正しいルールを広く知っていただくことが重要です。
LUUPでは、警察庁監修のテストをアプリ上で全員に受けていただいており、全問連続で正解しないとご利用できません。1問でも間違えると最初からやり直しとなる厳格な仕組みにより、ルールを正しく理解した方のみが利用できるよう設計されています。
2つ目は、「ルールを知っていても守らない人」への対策です。例えばGPSデータをもとに逆走や進入禁止エリアへの進入といった行為を検知し、違反内容に応じてスコアを加算していき、一定水準を超えるとアカウントを停止しています。さらに警察と連携し、違反した利用者の情報を共有いただき、適切にアカウント処理を行うことで、ルールを軽視する利用者をサービスから排除する仕組みを構築しています。
3つ目は、「知らないうちに起こる違反を防ぐこと」です。 地域ごとに車両の乗り入れ禁止などの細かいルールがあり、特に観光客の方には分かりづらい面があります。そこでLUUPでは、乗車前に目的地ポートを設定いただくことで、ルート上にある特有の規制区域を自動検出し、個別にアラートを表示します。さらに、危険な大通りを避けた安全な裏道をナビゲートし、初めての場所でも安心して利用できるようにしています。

将来的には、全車両にカメラを搭載し、自動運転化することで、ほぼすべての違反を遠隔・現地で検知可能な状態にすることを目指しています。しかし現状では、すべてを自動で検知することはできないため、人的オペレーションも含めて現場でできることを最大限行っています。
飲酒運転への対策を例に挙げると、繁華街などの飲酒リスクが高い場所では週末や夜間にポートへ警備員を配置し、利用者に対して抜き打ちでチェックするなど、技術開発と並行して現場での誠実な運用も徹底しています。
利用者の安全確保には、「技術への投資」と「現場での誠実な運営」の両輪が不可欠だと考えています。このように利用者の方々が安心して使えるように、今後もさらに改良を重ね、より安全なモビリティ社会を実現していきたいと思っています。
<構成/古田島大介 撮影/岡戸雅樹>
あなたにおすすめの記事

Luup岡井社長「キャリア形成は筋トレと同じ」 若いうちに圧倒的な量をこなして成長したいなら、自ら高い負荷を選ぶ覚悟を

「経験は8割が思考力でカバーできる」伝説の学生起業家に教わる“本当に役立つ大学生活の過ごし方”<編集後記>

コロナ禍で大学生活を送った教職志望の学生が「Z世代の企画屋」を創業するまで

「35歳までに結果が出なければサラリーマンに戻ろう」12年連続増収増益…“圧倒的成長企業”が生まれたワケ

「恋愛はコスパもタイパも悪い」は本当か?モテコンサルが語る恋愛と仕事の意外な共通点<編集後記>

「センスより『やる気』がある人が長期的に結果を出す」北の達人木下社長が明かす“成長する若手に共通する特徴“

「安定と挑戦の両立」一代で売上1兆円を見据える経営者が語る“最高のキャリア選択”

「年収1300万円では足りなかった」メガバンク出身女性起業家が明かす“起業の真相”

LUUP創業者の本音「経営は大変なことばかり」…改めて考えた“仕事が楽しい”とはなにか<編集後記>

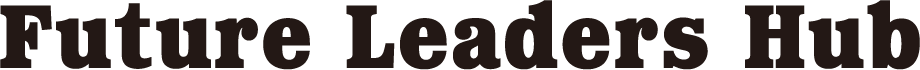
 Future Leaders Hub編集部
Future Leaders Hub編集部