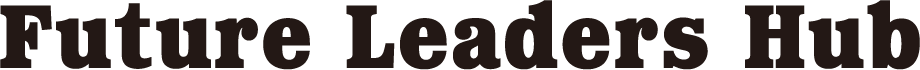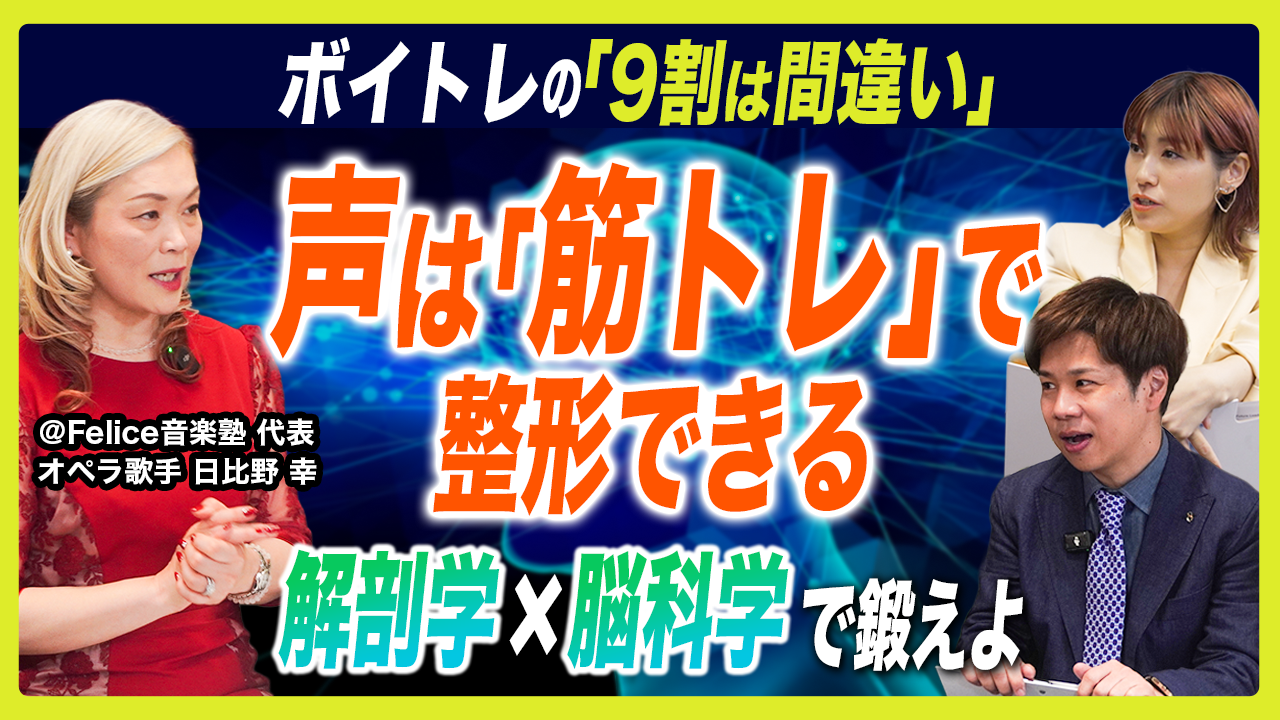「経験は8割が思考力でカバーできる」伝説の学生起業家に教わる“本当に役立つ大学生活の過ごし方”<編集後記>
先日、大学生から就職活動に関する相談を受けました。
「学生時代に、どんな経験をしておくべきですか?」
これまでも大学生から就活の悩みをたくさん聞いてきましたが、代表的な悩みのひとつが「経験のなさ」です。
「自分はサークル活動しかしてこなかった」
「インターンをいくつもやっている友達がいる」
「いろいろな経験をしなきゃと焦るけれど、何をすればいいのか見えない」
思い当たる人もいるのではないでしょうか。留学や旅行、コンクールで優勝、部活で表彰など“きらびやかな経験”はSNSで流れてきやすいので、それを見て「自分は経験値が低い」と嘆いている人もいそうです。
「経験はあまり重要視していない」
私自身を振り返ってみると、大学生の時はバックパックを背負って海外をあちこち飛び回っていたので、就活を始めた当時、「いろいろな経験をしていていいよね」と周囲からうらやましがられたこともあります。
でも、就職活動の面接では海外旅行について話すことはありませんでしたし、今の仕事でも旅の“経験”が直接役立っていると感じることはほとんどありません。(夜行バスは苦にならず、野宿も平気という旅の特技が、思わぬ場面で役に立ったことはありますが…)
“経験”は仕事の上で、どれほど必要なものなのでしょうか?
今回、インタビューした北の達人コーポレーションの木下勝寿さんの答えは「経験はあまり重要視していない」でした。
木下さんと言えば、 “伝説の学生ベンチャー”と言われる「リョーマ」のメンバーのひとりです。
「リョーマ」は現役大学生を中心に作られたベンチャー企業として一世を風靡。木下さんをはじめ上場企業の経営者を多数輩出しています。
私の学生旅行の“経験”と違って、学生起業なら直接仕事に役立ちそうに思えます。それにもかかわらず、学生起業の「経験」をしてきた木下さんが“経験”を重視しないというのは興味深い話です。
テスト問題と違って、仕事は答えがひとつでない
“経験”の価値を考えるため、ちょっと学校のテストに置き換えて考えてみましょう。
学校のテストでは“経験”はとても便利です。どんなに難しい問題でも1回解いたことがあれば、すぐに答えが出せるでしょう。まるで、試験問題が“昨日の授業そのまま”だったときのあの感じです。
では、仕事ではどうでしょうか? お客さんを増やす、クリック数を増やす、視聴数を増やす……。ある程度は、これまでの“経験”で答えが出せるかもしれません。
ただし、テスト問題と違って、仕事は答えがひとつではありません。“経験”だけに頼ってしまうと、「もっと良い答え」や「誰も思いつかなかった答え」にたどり着けなくなるかもしれません。
たとえば、普段お客さんが1000人の店を1200人に増やした“経験”のある人は、これまでの“経験”を生かして別の店でも集客に成功するかもしれません。それ自体は良いことです。
でも、“経験”ばかりに縛られてしまうと、「別のアイテムをつくって、1人当たりの購入金額を増やす」「実際に足を運ぶ人の数よりも、ネットで買い物する人を増やす」など別の発想や答えを生み出しづらくなります。
“経験”だけでは「もっと面白い仕掛け」や「新しい価値」を生み出すことは難しいのです。
論理的に考えて導き出す答えこそ役に立つ
いまは時代の変化が激しいため、“経験”だけに頼っていると急に“試験科目”が変わって“正解”さえ出せなくなってしまうことだって不思議ではありません。
きのうまで数学の試験だったのに、きょうは急に体育の試験が始まった――。そんな変化が、今の社会では普通に起こります。
“経験”よりも大切なものはなんでしょうか?
木下さんによると、それは「思考力」です。問題に直面したとき、過去の経験から得られる答えよりも、論理的に考えて導き出す答えのほうが、はるかに多くの場面で役に立つといいます。
木下さんは「問題を解くときは8割が思考力でカバーできる」と話していました。
確かに、日々の業務では、状況を整理し、課題を見極め、解決策を考える「思考力」が求められる場面がたくさんあります。
では、「経験」は必要ないのでしょうか? もちろんそんなことはありません。木下さんは、リョーマでの「経験」で「仲間に恵まれて『基準値』が上がった」そうです。
ダメな自分を認識し、「どうすれば優秀な仲間に追いつけるか?」と考える。営業のノウハウを学ぶ“経験”ではなく、仕事の基準値そのものを引き上げるような「思考の経験」です。
多様な「経験」の積み重ねから育まれる
私の学生時代の旅でも、バス停を間違えて目的地にたどり着けず困っていたとき、親切な人に助けてもらったなんてことが何度もあります。そんな「経験」が、「自分が失敗しなければ、こんな素敵な出会いはなかったはず」と考えるクセにつながっています。
かっこよく言うなら、「目の前の世界を斜めから眺め、予定通りに進まないことを楽しむ思考」が育まれたという「経験」でしょうか。
そうした「思考力の軸」は、やはり多様な「経験」の積み重ねから育まれるのだと思います。
逆に、いろいろな仲間や、旅先での出会いや気づき、仕事での失敗、そうした「経験」を積んでおかないと「思考力」は鍛えられない。
「経験」は「思考力」を鍛えるために積むものなのです。
「答えは質問の不幸である」という言葉があります。あなたが必要とする「経験」は“正解”を知るためのものではなく、「“正解”以外の問い」を見つけるためのもの。そんなふうに捉えることができるかもしれません。
木下さんはインタビューで「ピッパの法則」について教えてくれました。「ピッと思ったら、パッとやる」で、「ピッパの法則」です。
木下さんらしいユーモアと実践知が詰まった言葉ですが、それは「能率が上がる法則」だけでなく、「たくさんの『経験』を積む法則」でもあります。
どの「経験」が、何につながるかわかりません。逆に、目指すゴールに必ずつながる“経験”なんてものは、ほとんど存在しません。
「よかった」「面白かった」「ヤバイ」で終わらせない
学生起業集団「リョーマ」の名前の由来である坂本龍馬はこんな言葉を残しています。
「人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある」
幕末の混乱の中で、龍馬は既存の枠にとらわれず、新しい道を切り拓こうとしました。当時の当たり前ではない「経験」をたくさんしたことで、薩長同盟や大政奉還などを成し遂げることができたのだと思います。
冒頭の大学生の質問に戻りましょう。
「学生時代に、どんな経験をしておくべきですか?」
たくさんの人や街や本に出会い、自分だけでは気づけなかった世界に飛び込んでみてください。そして、「よかった」「面白かった」「ヤバイ」だけで終わらないように、短くてもそれを言葉にしてみてください。
それがきっと、新しい道を切り拓く「思考力」という名のあなたの武器になるはずです。
「#シゴトズキ・トップランナーの思考」でも、あなたの「経験」や「思考力」につながる動画をどんどん公開していきます。動画を視聴して、あなたが感じたことを言葉にしたら、ぜひコメント欄に書いてください。あなたの「思考」を楽しみにしています。
<文/清水俊宏 撮影/岡戸雅樹>
あなたにおすすめの記事

週6日17時間労働でも辛くなかった。 “たたき上げ経営者”が語る「努力と工夫で人生は変えられる」

「仕事が”楽しい”と感じたことは一度もなかった」Luup創業者が明かす“ハードモード”をあえて選ぶワケ

「年収1300万円では足りなかった」メガバンク出身女性起業家が明かす“起業の真相”

「船が形になる過程に大きなやりがい」造船会社トップが明かすリーマン・ショック後の再建と新たな挑戦

北の達人・木下勝寿社長が語る「人の心を読み取る力」—若いうちに接客業を経験すべき理由とAI時代の人間力

気鋭のZ世代経営者が明かす「“SNSネイティブ世代”の正体」

三菱UFJ銀行から結婚相談所代表へ ― 勝倉千尋氏が明かす「好きなこと」「得意なこと」「お金になること」の交差点の見つけ方

Luup岡井社長「キャリア形成は筋トレと同じ」 若いうちに圧倒的な量をこなして成長したいなら、自ら高い負荷を選ぶ覚悟を

“やめていい線引き”が背中を押す——剛腕経営者から学ぶ「撤退ラインがビジネスには欠かせない理由」<編集後記>