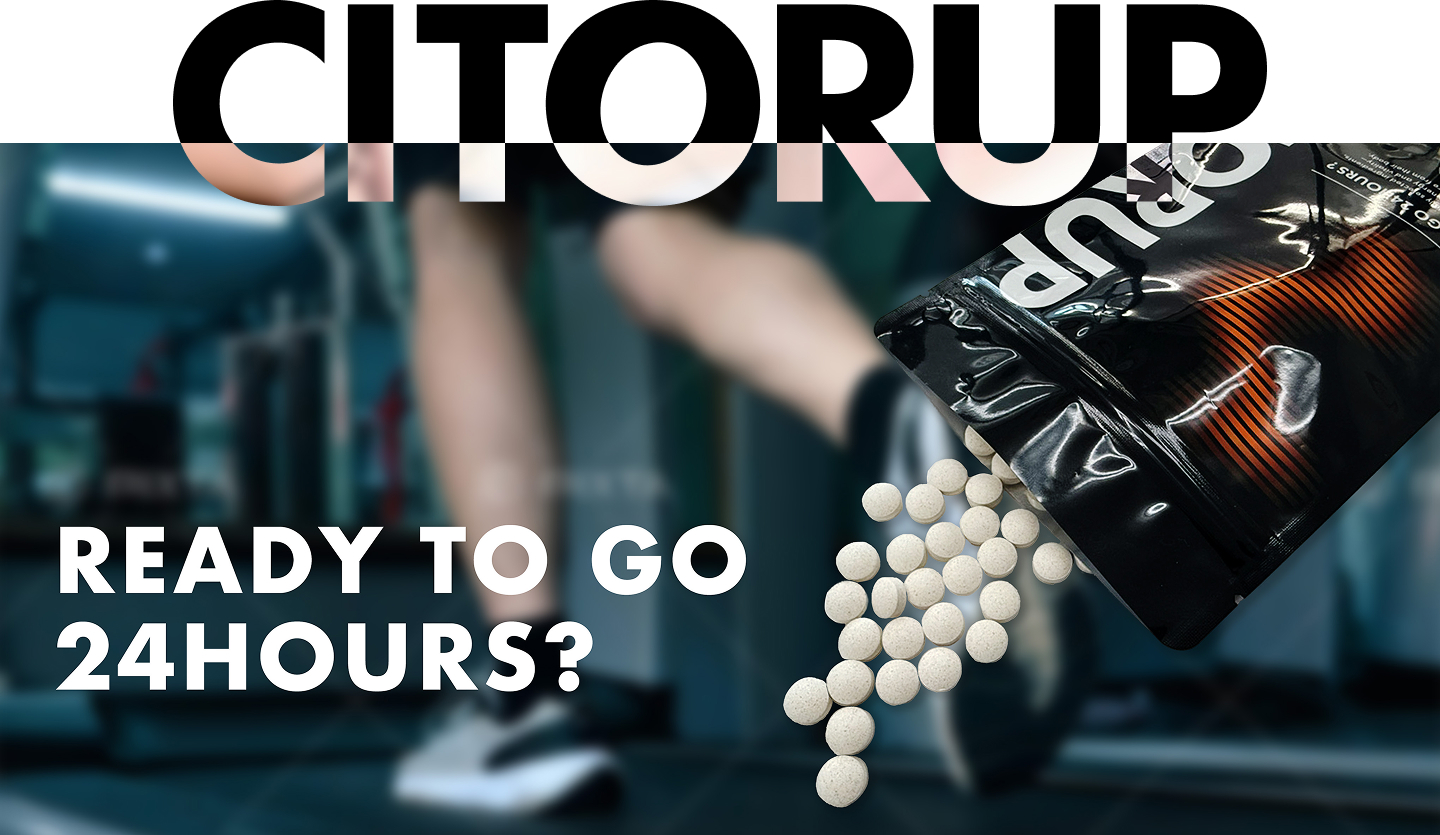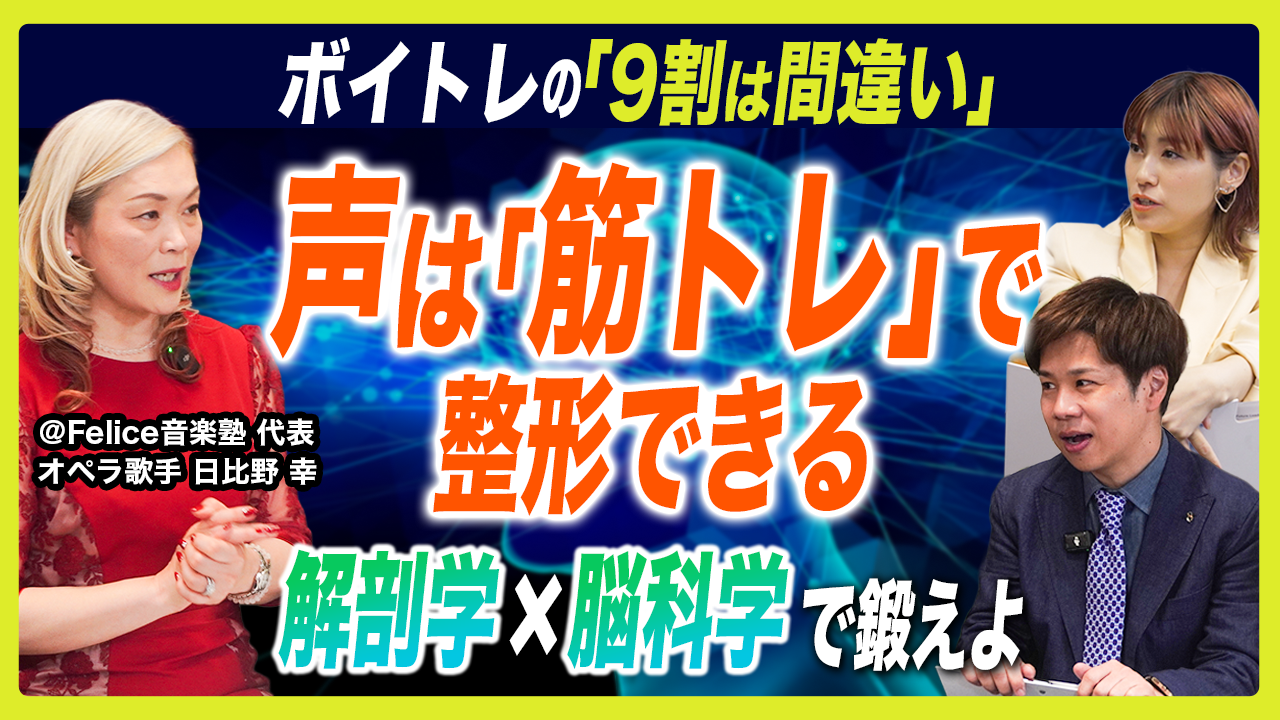「8時間じゃ足りない」働き方改革に違和感を覚え独立した経営者の意外なキャリアパス

「お金って、『ありがとう』って言われた数だけ稼げると思っているんですよね」
株式会社オトミ代表取締役社長、井元恒氏は、自身の仕事観をそう語ります。大学では地球科学を学び、岩石を研究していたという異色の経歴の持ち主。そこから一転、ものづくりの世界に飛び込み、商社マンとしてキャリアをスタートさせました。
仕事に熱中するあまり「8時間じゃ足りない」と感じ、働き方改革を機に独立。現在は、金属部品の専門商社である株式会社オトミと、ものづくりメーカーの株式会社ワイテックという2社の経営を手掛けています。
研究者から商社マン、そして経営者へ。そのキャリアを突き動かしてきた情熱の源泉とは何か。そして、未来を担う若者たちに何を伝えたいのか。井元氏の哲学に迫ります。
大学で学んだのは「課題解決へのアプローチ」
兵庫県神戸市で生まれ育ち、大学進学を機に故郷を離れた井元氏。大学では地球科学を専攻し、大学院まで進んで岩石の研究に没頭していたといいます。
「その辺の石ころに45億年の歴史が詰まっているわけですよ。この石がどこから来て、どういう経緯を辿って今ここにあるのか。その記録を読み解くのがすごく楽しくて、そればっかりやっていましたね」
研究室で日々使う実験器具は「メイド・イン・ジャパンか、メイド・イン・ジャーマニー」のどちらかだったといいます。その経験から「日本のものづくりってすごいんだな」と実感し、資源関係への就職が王道とされる中、ものづくりの分野へ興味を抱くようになったそう。
しかし、就職活動はリーマンショックの真っ只中。メーカーへの道は厳しく、地球科学出身であることに難色を示されることも少なくありませんでした。それでも、ものづくりへの関わりを諦めなかった井元氏は、商社という選択肢を見出します。
「別にメーカーじゃなくても商社でものづくりに携われるなって考えて。そもそも大学での学びが直接的に仕事に結びつかなくてもいいと思うんです。大学っていうのは、考え方を学びに行くところで、理系は理系的なアプローチで、文系は文系的なアプローチで、わからないことをどう解決していくか、その方法を学ぶ場所。たまたま僕がその考え方を学んだのが地球科学という分野だっただけなんです」
仕事とは、突き詰めれば「みんなが困っていることを解決すること」。その課題解決へのアプローチ方法を大学で学んでいれば、どんな分野でも活躍できる。井元氏の言葉は、専門性に縛られがちな学生たちの視野を広げてくれるのではないでしょうか。
「時間で区切られる働き方」への違和感
商社に入社後、井元氏は仕事の面白さにのめり込んでいきます。特に熱中したのが、顧客から預かる「設計図」を形にしていくプロセスでした。
「お客さんが書く設計図って、設計者の夢とわがままが詰まっているんですよ。『こういうのがほしい』という理想が描かれているんですが、現実的にどう作ればいいのか、と。それをどこの会社が持つどんな機械を使えば作れるんだろう、と考えるのがすごく楽しかったですね」
大阪、高知、神奈川と拠点を移しながら、仕事に没頭する日々。しかし、世の中で「働き方改革」が叫ばれるようになると、井元氏の中に違和感が生まれます。
「もともと私がいた会社は、結果で管理されていたんです。結果が出ていれば半日ゆっくりしてもいいし、稼げていないなら12時間働きなさい、と。その考え方がすごくしっくりきていたんです」
それが、突然「1日8時間」という時間で管理されるように。仕事が好きで、もっと働きたいという思いがあった井元氏は、時間で区切られる働き方に疑問を感じ、「それなら」と独立を決意します。
株式会社オトミを設立し、前職と同じ金属部品の商社として事業を開始。さらに、商社としてものづくりに携わる中で「自分でものを作りたい」という気持ちが芽生え、メーカーである株式会社ワイテックを事業承継。現在は2社の経営を担っています。

もし今学生なら「自分の分身を作って働かせる」
もし、今の知識を持ったまま学生に戻ったら、どんな働き方を選びますか。そう尋ねると、井元氏から意外な答えが返ってきました。
「いわゆる“令和の働き方”をするかもしれないですね。自分の分身を作って、その人に働かせるかな。AIやITツールで自分で分身をつくり、任せられる部分はテクノロジーに任せるという考え方です。例えば、学生時代に家庭教師のアルバイトをするとしたら、生徒の志望校の過去問をAIに読み込ませて、対策問題を作ってもらうかもしれない。もし起業するなら、昔、友人とやろうと考えていた放置自転車のリサイクル販売で活用しますね」
どの部品を使えば自転車を修理できるか、そのデータをAIに学習させる。いずれは自転車の写真を撮るだけで、必要な部品をAIが指示してくれるようになれば、経験者でなくても事業に携われるようになるといいます。
「AIの学習にはとにかく時間がかかる。でも、学生には時間がある。試してみる時間があるんです」
テクノロジーをいかに使いこなし、自分の時間を生み出すか。それは、これからの時代を生きる若者にとって必須のスキルになるのかもしれません。
半分できたら上司に相談。100点じゃなくてもいい
社会人になって初めて「怖い」と感じたのは、顧客から初めて注文をもらった時だったと井元氏は振り返ります。
「まだ社会人になって3~4か月の若造に、何百万円もの仕事を『じゃあ、お願い』と任されたとき、その責任の重さに震えました。それまではアポを取って会社説明をするだけで責任はなかった。でも、注文書を渡された瞬間に、納期までにものを作らなければいけないという責任が生じた。楽しいというより、怖いと思いましたね」
入社数か月でも大きな裁量を与えられ、一人で仕事を進めることが多かった新入社員時代。そんな当時の自分にアドバイスするなら、どんな言葉をかけますか。
「『半分できたら上司に相談しろ』って言いますね。100点じゃなくてもいいよ、と。当時は負けてなるものか、と自分の中で100点にしないと気が済まなかった。でも、知識も経験も乏しい中で遠回りすることも多かったんです」
上司や先輩は忙しいだろう、と遠慮してしまう気持ちは誰にでもあるでしょう。しかし、相談される側になった今、むしろ相談してくれた方が安心すると井元氏は語ります。
「一人で考えるより、人と打ち合わせをすれば1+1が2.5になったりする。いい仕事をするためには、一人で抱え込んではいけないんです」
求めるのは「素直で嘘をつかない」人材
最後に、どんな若者と一緒に働きたいかと尋ねました。井元氏が採用において絶対に外さないという条件は、たった一つでした。
「素直で嘘をつかないこと。これだけです」。
その背景には、前職時代に社内の人に対して嘘をついてしまい、今でも後悔しているという自身の経験があります。
「身内から疑われるのって、かなり厳しい。だから、うちの社員には『絶対嘘はつくな』と言っています。どんな失敗をしても、起きた事象に対しては怒るかもしれないけど、あなた自身を怒ることはないから、と」
その上で、若いうちはがむしゃらに働くことの価値も説きます。
「若いうちにワークライフバランスの“ライフ”に重きを置きすぎた人で、30代、40代になって活躍している人をあまり見ないんです。もちろんライフは大事ですが、若いうちは多少“ワーク”に振っておくと、将来すごくいい仕事ができるようになる。将来への貯金みたいなものですね」
当たり前のことを愚直にやり続ける。その誠実な姿勢こそが、信頼を築き、人を動かし、やがて大きな仕事を成し遂げるための揺るぎない土台となるのです。

あなたにおすすめの記事

借金4億5000円からの再建…元リクルート経営者が「プロ野球選手の夢」の先に見出した理念と情熱

司法試験断念から月収100万円も「ありがとうと言われない仕事は虚しい」…波乱万丈のキャリアを歩んだ“二刀流社長”の教え

「何でも動いてみないとわからん」繊維商社からクリエイティブへ…挑戦の連続が生んだ“異色のキャリア”

「どうせもうアウトだからイチかバチか」大学中退、指の大怪我、恋人の裏切り…捨て鉢から始まった町工場社長の大逆転ストーリー

挑戦が循環する社会へ…「部活スポンサープラットフォーム」を手掛ける経営者の情熱

「生意気だ」と言われた“学歴ゼロ”の若者が21歳で独立。創業から会社売却、上場に再挑戦するまで

「とにかく人に喜ばれる仕事につきたい」IT企業経営者が振り返る“天職を確信できた瞬間”

「起業は逃げに等しいかもしれない」大手IT企業から独立した経営者が明かした“自由を求めた本音”

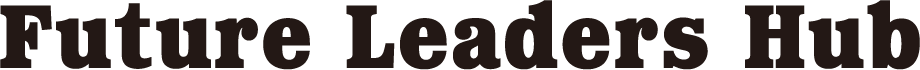
 Future Leaders Hub編集部
Future Leaders Hub編集部